詐欺被害者からの返還請求にお困りの方へ
銀行口座の売買・譲渡に関与してしまい、詐欺被害者やその代理人弁護士から返還請求を受けてお困りではありませんか?本ページでは、口座売買の法的リスクと具体的な問題解決方法についてご説明します。
銀行口座の売買・譲渡・レンタルは、有償・無償にかかわらず犯罪です。
すでに関与してしまった方は、早急に専門家に相談することをおすすめします。
1. 口座売買・譲渡の危険性
銀行口座の売買・譲渡・レンタルは、犯罪収益移転防止法違反や詐欺罪の幇助にあたる犯罪行為です。
刑事上の責任
- 犯罪収益移転防止法違反により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性
- 詐欺罪の幇助として最大10年以下の懲役に処される可能性
- 逮捕・起訴により社会的信用を失う
- 前科がつく可能性
民事上の責任
- 詐欺被害者から損害賠償請求を受ける
- 口座に振り込まれた詐欺被害金全額の返還義務が生じる可能性
- 多額の債務を抱える
- 裁判費用の負担
口座売買が急増する背景
経済的困窮やSNSでの副業勧誘の増加により、口座売買のトラブルが急増しています。特に、コロナ禍以降の経済情勢の悪化や、闇バイト・副業詐欺の横行により、安易に口座を売却・譲渡してしまうケースが増えています。
2. 口座売買を持ちかける手口
口座売買・譲渡は様々な手口で持ちかけられます。主な誘い文句や手口を理解し、注意することが重要です。
副業を装った勧誘
- 「口座を貸すだけの簡単な副業です」
実際は犯罪行為の加担です - 「口座をレンタルするだけで月5万円」
犯罪収益移転防止法違反となります - 「海外送金の受け取り代行」
マネーロンダリングに加担することになります - 「不要な口座を高額買取」
詐欺などの犯罪に使われる可能性が高いです
お金配りを装った勧誘
- 「お金配りの代行をしてほしい」
犯罪組織への資金提供の可能性があります - 「YouTuberのお金配り企画の協力者募集」
詐欺の可能性が高いです - 「慈善活動のための口座提供」
善意を悪用した詐欺の典型です - 「SNSフォロワー増加企画への協力」
架空の企画で口座を騙し取る手口です
闇金関連の勧誘
- 「口座を担保にすれば資金援助」
さらなる借金地獄に陥る危険があります - 「口座を提供すれば借金を無くす」
詐欺的な話法であり、実現することはありません - 「口座売却で借金返済資金を得る」
犯罪に加担し、さらに大きな法的問題を抱えることになります - 「闇金からの催促を止める方法」
新たな詐欺の可能性があります
SNSでの誘い手口
- DMやメッセージでの突然の勧誘
見知らぬ人からの提案には要注意 - 「フォロワーが多い」「認証済みアカウント」を装う
偽アカウントの可能性が高いです - 「すぐに連絡先交換やLINEへの誘導」
証拠を残さないための手口です - 「期間限定」「今だけ」などの焦らせる文言
冷静な判断を妨げる詐欺の典型手法です
特に注意すべき最新の手口「口座レンタル」
最近では「売買」ではなく「レンタル」という言葉を使うことで、犯罪性を薄める手口が増えています。しかし、「レンタル」も「売買」も「譲渡」も法律上はすべて犯罪行為であり、刑事罰の対象となります。「一時的に貸すだけ」という言葉に騙されないようご注意ください。
3. 口座売買の刑事責任
口座売買・譲渡に関与した場合、以下のような刑事責任を問われる可能性があります。
3.1 適用される法律と罰則
| 法律 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|
| 犯罪収益移転防止法 第28条第2項 | 他人になりすますことや、譲り受ける目的で口座開設すること、預金通帳等を譲り渡すことを禁止 | 1年以下の懲役または 100万円以下の罰金 (併科あり) |
| 詐欺罪(刑法第246条) の幇助 | 口座が詐欺に利用された場合、詐欺罪の幇助として処罰される可能性 | 10年以下の懲役 |
| 組織犯罪処罰法 | 口座が組織的な犯罪に使用された場合に適用 | 犯罪の種類により異なる |
| 窃盗罪(刑法第235条) | 他人名義の口座から現金を引き出した場合に適用 | 10年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
3.2 逮捕される可能性
口座売買に関与した場合、以下の状況で逮捕される可能性が高まります:
- 複数の口座を売買した場合 – 単発ではなく複数回にわたる場合、悪質性が高いと判断される
- 高額な詐欺被害が発生した場合 – 売却した口座で大きな被害が出た場合、捜査が優先的に行われる
- 組織的な犯罪に関与した場合 – 犯罪組織との関係が疑われる場合
- 反省の態度が見られない場合 – 警察の任意の出頭要請に応じず、証拠隠滅の恐れがある場合
逮捕・起訴の流れ
口座売買の犯罪が発覚した場合、一般的に以下のような流れで刑事手続きが進みます:
- 警察からの呼び出し・任意での事情聴取
- 逮捕(最大72時間の身柄拘束)
- 検察への送致と勾留請求(最大20日間の拘束)
- 起訴判断(起訴または不起訴)
- 起訴された場合は裁判へ
3.3 刑事処分例
※具体的な処分内容は事案によって変わります。あくまで一例とご理解ください。
| 事例 | 状況 | 処分結果 |
|---|---|---|
| 初犯・反省あり (単発の口座売買) | 生活費に困り、SNSでの勧誘に応じて1つの口座を売却。捜査に全面協力 | 起訴猶予 (前科はつかない) |
| 複数口座の売買 | 複数の銀行口座を繰り返し売却。詐欺組織との関わりが認められた | 執行猶予付き懲役刑 |
| 組織的関与 | 口座ブローカーとして多数の口座を収集・売却。大規模詐欺に関与 | 実刑(懲役刑) |
重要なポイント
口座売買に関与した場合、犯罪性を認識していなかったとしても処罰の対象となります。「知らなかった」「騙された」という弁解は刑事責任を免れる理由にはなりません。ただし、反省の態度や協力的な姿勢は、処分を軽減する要素になる可能性があります。
4. 口座売買の民事責任
口座売買・譲渡は刑事責任だけでなく、民事上の重大な責任も発生します。特に詐欺被害者から多額の損害賠償請求を受ける可能性があります。
4.1 詐欺被害者からの返還請求
売却・譲渡した口座が詐欺に使用された場合、被害者は以下の法的手段で返還請求をしてくることがあります:
- 不当利得返還請求 – 口座に振り込まれた金額の返還を求める
- 損害賠償請求 – 不法行為(詐欺の幇助)に基づく損害賠償を求める
- 振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払請求 – 口座凍結後の残高から支払われる
振り込め詐欺救済法について
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)によって、詐欺に使われた口座が凍結され、その残高は被害者に分配されます。ただし、口座に残高がない場合や引き出されてしまった場合は、被害者は口座名義人に対して直接請求することになります。
4.2 損害賠償の範囲
民事訴訟で請求される賠償額は、以下のような内容を含む可能性があります:
- 被害金額全額 – 口座に振り込まれた詐欺被害総額
- 遅延損害金 – 法定利率(年3%)による利息
- 慰謝料 – 精神的苦痛に対する賠償
- 弁護士費用 – 被害者が負担した弁護士費用の一部
4.3 裁判例
| 判例 | 事案概要 | 判決内容 |
|---|---|---|
| 東京高裁 平成26年7月10日判決 | 詐欺グループに口座を提供し、詐欺被害が発生 | 口座提供者に対し、詐欺被害全額(約800万円)の賠償責任を認定 |
| 名古屋地裁 令和4年10月25日23 | SNSを通じた投資詐欺に口座を提供 | 口座提供者に対し、振込額を超える被害額全額の賠償責任を認定 |
| 東京地裁 平成28年3月23日判決 | 口座売買に関与し、詐欺に利用された | 詐欺を助長したとして共同不法行為責任を認め、全額賠償を命じる |
裁判例のポイント
多くの裁判では、口座提供者に詐欺の故意がなくても、口座提供行為によって詐欺行為を容易にしたとして、共同不法行為責任(民法719条)が認められています。この場合、詐欺被害の全額について賠償責任を負う可能性があります。
4.4 その他の民事上の不利益
- 口座凍結 – 売却・譲渡した口座だけでなく、本人名義の全ての口座が凍結される可能性
- 金融取引の制限 – 新規口座開設や融資などの金融サービスを受けられなくなる
- 信用情報への影響 – ローンやクレジットカードの審査に悪影響
- 就職・転職への影響 – 特に金融機関や信用を要する職業への就職に支障
5. 解決方法
口座売買により詐欺被害者から返還請求を受けた場合、状況に応じた適切な解決方法を選ぶ必要があります。以下に主な選択肢を解説します。
5.1 自己破産
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、財産を処分・分配することで借金の支払義務を免除してもらう手続きです。
自己破産のメリット:
- 原則として全ての債務が免除される
- 債権者からの取立てがすぐに止まる
- 最低限の生活は保障される(99万円までの生活費用や必要な家財道具は残せる)
自己破産のデメリット:
- 自宅など価値のある財産は処分される
- 官報に掲載され、ブラックリストに載る(7〜10年間)
- 一部の職業制限がある(破産者が就けない職業がある)
- 免責不許可事由に該当する場合は免責されない
自己破産が適している人:
- 返還請求額が高額で返済見込みがない
- 資産がほとんどない
- 収入が少なく、返済能力に乏しい
- 詐欺被害者からの多額の損害賠償請求に対応できない
自己破産の注意点
口座売買に関する債務が悪質な事案と判断された場合、免責不許可事由(破産法252条1項)に該当し、免責が認められないケースがあります。専門家に事前に相談することが重要です。
5.2 個人再生
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、債務を大幅に減額した上で、3〜5年の分割払いで返済する手続きです。
個人再生のメリット:
- 債務が最大で5分の1まで減額される
- 住宅ローンがある場合でも自宅を残せる可能性がある(住宅資金特別条項)
- 債権者からの取立てが止まる
- 自己破産に比べて社会的制約が少ない
個人再生のデメリット:
- 安定した収入が必要(返済計画の履行能力が必要)
- 手続きが複雑で時間がかかる
- 官報に掲載され、ブラックリストに載る(5〜7年間)
- 減額後の債務を完済する必要がある
個人再生が適している人:
- 返還請求額が高額だが、安定した収入がある
- 住宅ローンがあり、自宅を手放したくない
- 自己破産のデメリットを避けたい
- 債務の一部なら返済できる見込みがある
個人再生の返済額の目安
| 債務総額 | 最低返済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 債務総額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1,500万円未満 | 債務総額の1/5 |
| 1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円以上5,000万円以下 | 債務総額の1/10 |
5.3 任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、返済条件を変更する手続きです。
任意整理のメリット:
- 裁判所を通さないため手続きが比較的簡単
- 将来利息のカットや分割払いの合意が可能
- 官報に掲載されない(自己破産や個人再生と異なる)
- 財産を処分せずに済む
任意整理のデメリット:
- 債権者の同意が必要(交渉次第)
- 元金は基本的に減額されない
- 信用情報機関に事故情報として登録される(5〜7年間)
- すべての債権者と合意できるとは限らない
任意整理が適している人:
- 返還請求額が比較的少額である
- 安定した収入があり、分割返済が可能
- 債権者が交渉に応じる可能性がある
- 自己破産や個人再生のデメリットを避けたい
口座売買に関する注意点
詐欺被害者や代理人弁護士は、口座売買の関与者に対して厳しい姿勢をとるケースが多く、任意整理の交渉が難航する可能性があります。特に被害額が高額な場合は、合意が得られないことも多いため、事前に専門家の意見を聞くことが重要です。
5.4 各手続きの比較
| 項目 | 自己破産 | 個人再生 | 任意整理 |
|---|---|---|---|
| 債務減免 | 原則全額免除 | 最大80%減額 | 将来利息カット |
| 財産への影響 | 処分される | 基本的に残せる | 影響なし |
| 手続きの難易度 | やや複雑 | 複雑 | 比較的簡単 |
| 手続き期間 | 約3〜6ヶ月 | 約6ヶ月〜1年 | 約2〜4ヶ月 |
| 信用情報への影響 | 7年 | 7年 | 5年程度 |
| 官報掲載 | あり | あり | なし |
| 口座売買事案での適性 | 高額被害で返済困難な場合 | 安定収入があり一部返済可能な場合 | 少額被害や債権者が柔軟な場合 |
6. 当事務所のサポート内容
当事務所では、口座売買・譲渡に関するトラブルでお困りの方に対して、以下のような法的なサポートを行っています。
法的アドバイス
- 刑事責任・民事責任の範囲の説明
- 警察対応のアドバイス
- 詐欺被害者からの請求への対応
- 最適な解決方法の提案
債務整理のサポート
- 自己破産申立ての支援
- 個人再生申立ての支援
- 任意整理における債権者交渉
- 返済計画の立案
交渉・和解支援
- 詐欺被害者との和解交渉
- 分割払い等の条件交渉
- 和解書・示談書の作成
- 金融機関との対応
当事務所の対応の流れ
- 初回無料相談 – 現状と問題点の把握
- 解決方針の提案 – 最適な債務整理方法の提案
- 債権調査 – 詐欺被害者や代理人との連絡
- 方針に基づく手続き – 自己破産・個人再生・任意整理の手続き
- 債権者との交渉 – 必要に応じた和解交渉
- 手続き完了 – 債務整理の完了
- アフターフォロー – 生活再建のサポート
7. 依頼時の報酬基準
当事務所における口座売買問題に関する債務整理の報酬基準は以下の通りです。お客様の状況に応じて最適なプランをご提案いたします。
| 手続き | 着手金(税込) | 報酬金(税込) | その他費用 |
|---|---|---|---|
| 自己破産(同時廃止) | 385,000円〜 | なし | 裁判所予納金、郵便切手代など |
| 自己破産(管財事件) | 440,000円〜 | なし | 管財人報酬(20万円〜)、予納金など |
| 個人再生(住宅なし) | 385,000円〜 | なし | 裁判所予納金など |
| 個人再生(住宅あり) | 440,000円〜 | なし | 裁判所予納金など |
| 任意整理 | 22,000円〜 | 33,000円~ | 郵便切手代、振込代行費用 |
| 特定調停 | 55,000円〜 | 事案による | 郵便切手代など |
| 警察対応等のサポート | 55,000円〜 | 事案による | 交通費など |
分割払いについて
当事務所では、経済的にお困りの方のために、報酬の分割払いに対応しています。詳細はお問い合わせの際にご相談ください。
8. よくある質問
口座売買をしてしまいましたが、詐欺だとは知りませんでした。それでも罪に問われますか?
はい、口座売買・譲渡は「知らなかった」「詐欺だと思わなかった」としても、犯罪収益移転防止法違反として罪に問われます。同法では、口座の売買・譲渡行為そのものを禁止しており、目的を知らなかったことは免責の理由にはなりません。ただし、事案の悪質性によって量刑や処分は異なります。
詐欺被害者から数百万円の損害賠償を求められていますが、支払う義務はありますか?
裁判所の判例では、口座提供者(売却・譲渡した人)に対して、詐欺の共同不法行為者として損害賠償責任を認めるケースが多いです。口座が詐欺に利用されたことで被害が発生した因果関係があれば、たとえ詐欺の意図がなくても、民法上の損害賠償責任を負う可能性が高いといえます。ただし、具体的な状況によって異なりますので、専門家に相談することをお勧めします。
警察から連絡がありました。どう対応すべきですか?
警察から連絡があった場合は、まずは弁護士、司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで適切な対応方法のアドバイスを受けられます。
特に初期対応が重要ですので、すぐに専門家に相談してください。
自己破産すれば詐欺被害者への返還義務はなくなりますか?
基本的には自己破産により免責が認められれば、詐欺被害者への返還義務も免除されます。ただし、口座売買への関与が極めて悪質と判断された場合、「詐欺行為」として免責不許可事由に該当し、免責されないケースもあります。また、破産手続き前に財産を隠した場合なども免責されません。自己破産が適切な選択肢かどうかは、専門家と相談の上で判断することが重要です。
口座売買で得た報酬は返還する必要がありますか?
口座売買で得た報酬は不法原因給付(民法708条)に該当する可能性があり、一般的には口座売買持ち掛けてきた人に対して返還義務はないとされています。
しかし、口座売買に関連して詐欺被害が発生した場合は、その損害賠償責任を負うことになります。つまり、口座売買で得た数万円のために、詐欺被害額の数百万円の賠償責任を負う可能性があるということです。
口座売買に関して家族に連絡が行くことはありますか?
刑事事件として捜査が進んだ場合、警察が家族に事情を聞く可能性はあります。また、逮捕された場合は基本的に家族に連絡が行きます。
民事事件(損害賠償請求など)の場合も、訴状が自宅に送られるため、同居家族が知ることになる可能性が高いです。しかし、当事務所にご依頼いただければ、相手方からの連絡先を事務所に指定するなど、プライバシーに配慮した対応も可能です。
個人再生と任意整理はどちらが良いですか?
どちらが良いかは、返還請求額の大きさや収入状況によって異なります。個人再生は債務を大幅に減額できる利点がありますが、手続きが複雑で費用も高額です。一方、任意整理は手続きが比較的簡単ですが、元金の減額は難しいため、高額な返還請求には対応しきれないことがあります。口座売買に関連する返還請求の場合、債権者(詐欺被害者)が任意整理に応じない可能性もあるため、個別の状況を踏まえた専門家の判断が必要です。
司法書士と弁護士のどちらに相談すべきですか?
基本的に民事上の債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)であれば、司法書士でも対応可能です。ただし、司法書士の場合、取り扱える債権額に制限(140万円以下)があります。口座売買に関連する事案では、刑事上の問題もあるため、刑事対応ができる弁護士の協力を得ることもあります。当事務所では、必要に応じて弁護士と連携し、刑事・民事両面からのサポートを提供しています。
詐欺被害者が銀行口座を凍結したと言っています。解除できますか?
詐欺に利用された疑いがある口座は、銀行の判断または振り込め詐欺救済法に基づいて凍結されます。一度凍結された口座を個人の力で解除することは基本的にできません。また、口座売買に関与した場合、その口座だけでなく本人名義の他の口座も凍結される可能性があります。凍結が誤りである場合は、弁護士・司法書士を通じて状況説明や交渉を行うことは可能ですが、口座売買の事実がある場合は困難です。
贈与税は関係ありますか?
口座売買・譲渡で得た金銭については、それ自体は「贈与」ではなく「対価」とみなされるため、基本的に贈与税の対象とはなりません。ただし、脱税目的で口座譲渡を行った場合など、税法上の問題が別途生じる可能性はあります。また、口座売買に関連する詐欺被害の損害賠償や和解金の支払いは贈与ではないため、贈与税の対象外です。
9. お問い合わせ
口座売買でお困りの方は、まずは無料相談をご利用ください。ご状況をお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。
お電話でのご相談
相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
LINEからのご相談
24時間いつでもお問合せいただけます。以下から友達登録の上、ご連絡ください。
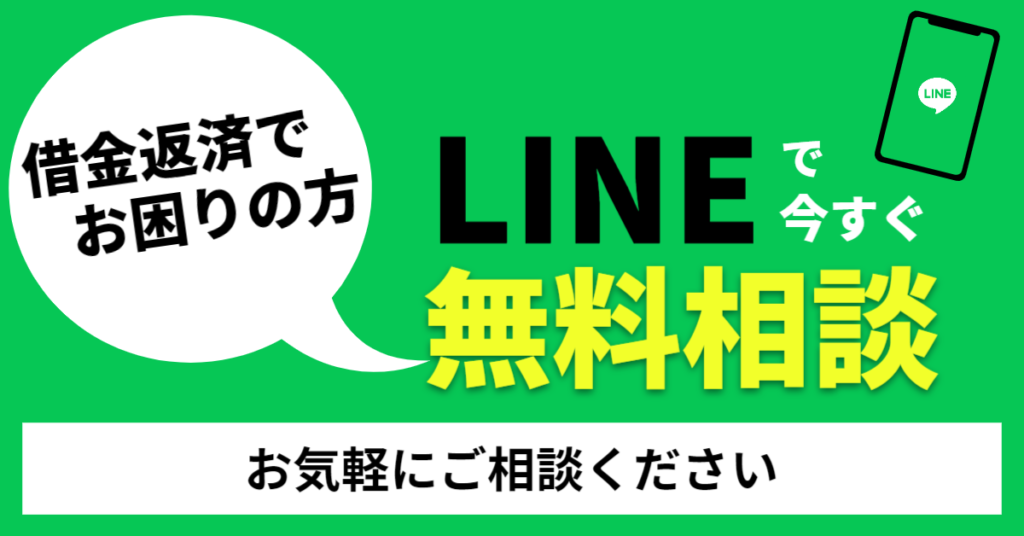
※土日祝日のご相談も可能です。
※テレビ電話相談も承っております。
お悩みの方へのメッセージ
口座売買や譲渡に関わってしまい、詐欺被害者からの返還請求や警察からの連絡に不安を感じている方も多いでしょう。このような状況は一人で抱え込まず、専門家に相談することが解決への第一歩です。
当事務所では、刑事・民事両面からのサポートを提供し、最適な解決策をご提案します。早期に適切な対応をすることで、問題解決の可能性は大きく広がります。まずは無料相談でお気軽にご相談ください。
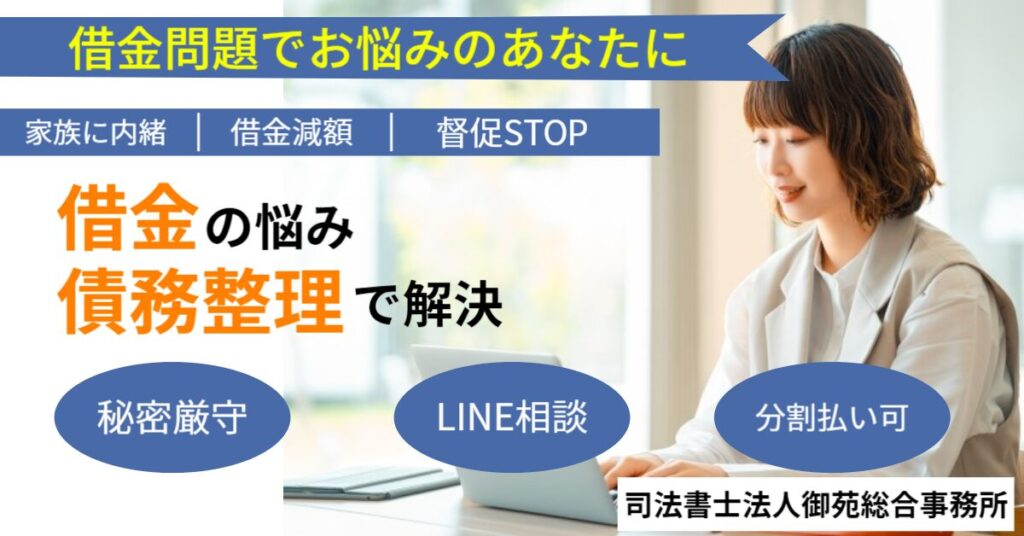

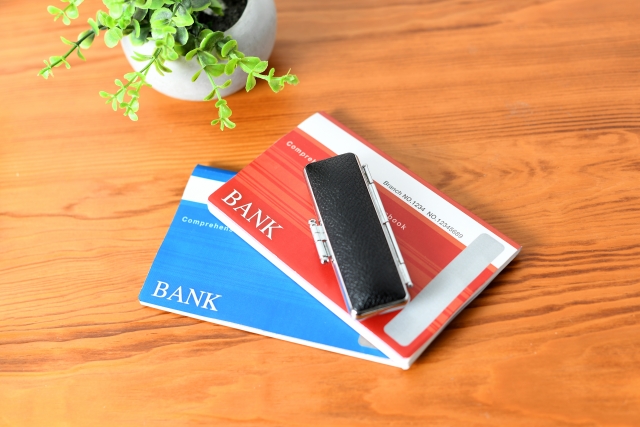
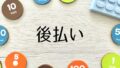

コメント